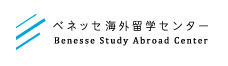海外大・国内グローバル大学入試に必要なテスト対策、「いつから・何した」体験談 ~カリフォルニア大学サンディエゴ校 A.K.先輩~
英語圏の大学に出願する際、ほぼ必須となるのがTOEFL®やIELTS™といった外部英語試験のスコア。さらに、アメリカの大学では学力の証明としてSAT®などのスコアも求められることが多く、複数の試験対策が欠かせません。海外大学を目指した先輩たちは、どのように試験対策を始め、どのような工夫を重ねてきたのでしょうか。カリフォルニア大学サンディエゴ校に進学したA.K.先輩に、学習スタート時の取り組みから実体験に基づくアドバイスまで詳しくお話を伺いました。
※ここでご紹介している内容は個人の体験です。実際に準備する際は、必ず最新の情報をご確認ください。

過去問の演習・復習・分析の繰り返し。対策コースを活用しつつ、問題の傾向を捉えて攻略!
今回の「ラボ協力隊」

A.K.先輩
アメリカ カリフォルニア大学サンディエゴ校 2年生、神経科学とジェンダー批評学をダブル専攻。
中3の時に興味のある分野に関する海外論文を読んだことから海外大進学を考え始めた。幼少期からの空手・ダンス、高校時には研究論文を執筆するなど課外活動は多岐に渡る。
Q. 受けたことのある外部英語試験は? 受験のきっかけや時期も教えてください!
高1秋からTOEFL®、高2秋からSAT®対策を開始。各3回受験で目標スコアに到達!
A.K.先輩が受けた外部英語試験
- 1. TOEFL®:高1の10月〜高2の冬
2. SAT®:高3の5月・8月・12月(対策は高2の10月〜) - *この他、小学校の時に英検(準1級)の受験経験あり
TOEFL®:高1の10月〜高2の冬
高1の10月から対策し始め、高2の冬に受験した3回目の試験で目標のスコア(95)に手が届きました。
中3の時に海外大学受験を視野に入れ、高1の夏に海外留学に行く予定でした(新型コロナウイルスの流行で結局行けなかったのですが…)。海外大学受験にはもちろん、海外留学プログラムに参加するにもまずはTOEFL®スコアが必要だと知ったので、それから対策を始めました。
TOEFL®対策を始めた時の私の英語レベルは、高いスコアを取るために必要とされる長文読解能力・語彙力にはまだまだ及びませんでした。しかし、日本国内のトップレベル大学の受験も当時は視野に入れていた私としては、海外大対策のためのTOEFL®受験で培った英語力はいずれ国内大学受験にも活きると思い、TOEFL®対策は続けました。
SAT®:高3の5月・8月・12月(対策は高2の10月〜)
高2の10月から対策し始め、高3の5月、8月、12月の計3回受験し、3回目で目標のスコア(1400)に到達しました。
行こうと思っていた海外留学が中止になってしまったことで、海外大進学に向けて本腰を入れ始めたのが高1の夏でした。私の場合、海外大学はアメリカに絞って受験するつもりだったので、米国大学受験とそれに伴う奨学金申請にはSAT®スコアが必要不可欠だったこともあり、納得のいくスコアが取れるまで受験しました。
この他、海外大受験には活用しませんでしたが、小学校中学年の時に英検準1級を取得しました。小学生の頃から両親のサポートもあり英語を勉強していたので、勉強の成果を形にする手段として英検が一番有効だと考えました。
Q. 各テストの特徴は? 気をつけたいポイントもあればぜひ!
過去問を解き、復習・分析するのが効果的。毎回時間を測ってスピード感に慣れよう。
英検の特徴
英検は日本国内で英語力を確認するテストとしてメジャーなのもあって、対策用の参考書がたくさん出ていますよね。それはReading・Writing・Listening・Speakingの問題構成において、ある程度のスタイルが確立されていて、特徴を押さえれば攻略できることの証明だと思います。
Readingであれば、設問の順番は段落順に対応していて、パッセージも設問も上から順番に解くことがコツです。Listeningは問題の傾向を事前に過去問で予習し、出題音声の前に問題文を先読みできる時間でいかに焦らず目を通せるかにかかっていると思います。Speakingは過度に緊張しないように入室・退出時の試験官とのコミュニケーション方法を押さえておくことが助けになるでしょう。
一番対策のしがいがあるのはWritingです。Writingは与えられた時間で決まったお題に対する自分の考えを自由に書くのではありません。採点者が採点する上での「決まった形式」というものが存在します。この形式に則らずにエッセイを書いた場合、間違いではありませんが、あくまでテストで良いスコアを目指す上で、採点者の手を煩わせれば煩わせるほど点の獲得は遠のく、と考えた方がいいでしょう。
まずお題に対する自分の考えをブレインストーミングしますよね。その上で、自分の考えを何段落に分けて書くのか、どのような論理展開で書くのか、そしてどのような言葉のトーンで書くと好印象なのか。
この一連の流れを練習し、慣れて速くしていくことがWriting力の向上、そしてWritingでの高スコア獲得に繋がると思います。そしてこれは英検に限らず、TOEFL®のWriting対策にも活きるでしょう。
TOEFL®の特徴
英検同様、過去問を通して問題の傾向やパターンを予習することがコツです。
Readingに必要な語彙力、問題傾向の理解度を上げるためには過去問を解き、逐一復習することが一番の近道だと思います。Writingに関しても英検と同じく、与えられた時間の中で自分の考えを論理的に文字にするまでにかかるスピードをいかに早くするか、そしてそのプロセスに慣れるかです。
TOEFL®の場合はパソコンを使っての試験なので、タイピングの速さはWritingに少なからず影響すると思います。また、周りの受験者と同時にSpeaking試験を受けることになるので、その時いかに集中しハキハキと話すことができるかも重要だと思います。
SAT®の特徴
日本の高校に通っている生徒であれば、数学はほとんど対策の必要はないでしょう。唯一言えることは油断せず問題文をしっかり読み、見直しをすることです。
読解に関しては、TOEFL®以上に読解スピードが要求されること、問題文のテーマがある程度決まっていることを踏まえて、こちらもやはり過去問を解き、復習して分析することが近道だと思います。問題文のテーマ(物語・時事・論文等)を押さえられれば、読解に必要な語彙力が分かってくると思うので、自分の今の語彙力に足りていない分野の文章を読むなどして語彙を増やせると思います。
また、とにかく時間がないので、本番で焦ることがないよう、問題を解いていくスピード感に慣れるために毎回時間を測って過去問に取り組むことが大切です。
Q. はじめの一歩として、どんな勉強から手をつけた?
程よく受動的に学べる専門コースに入会。海外大を目指す仲間と情報交換もできた!
TOEFL®
私は自分一人で地道にテストまで頑張れる自信がなかったので、ある程度受動的に勉強できる環境を求めてベネッセ Route G(当時はGlobal Learning Center* / 以下、旧GLC)のTOEFL®対策コースに入りました。
同じ高校に海外大受験をする人がほとんどおらず身近なリソースも少なかったので、海外大学受験のコミュニティーを求めていたというのもありました。結果として、同じ世代のTOEFL®、SAT®受験準備をしている子たちと情報交換ができる点からも、Route G(旧GLC)に入会したのは個人的にとても良い判断だったと思います。
TOEFL®対策に必要なテキストは、ほぼ全てその対策コースで使用していたPrinceton ReviewのTOEFL®の対策問題集+副教材でまかない、あとは1冊追加でTOEFL®の公式過去問集を自分で購入しました。伸びるのに時間がかかると思ったReadingとWritingに重点を置いて、過去問を解きつつ対策を始めました。
*Global Learning Center:現在のRoute Gの前身
SAT®
TOEFL®対策と同じ理由で、Route G(旧GLC)のSAT®コースにお世話になりました。対策に使用したのは、SAT®コースで使用されていたCollege Board*のSAT®公式問題集や、実際のSAT®試験より難易度が高いと言われているPrinceton ReviewのSAT®過去問題集です。
数学の過去問は、英語の勉強に疲れた時の息抜きにしていました(冗談でも自慢でもなく、そのくらい簡単に感じられると思います)。私は英語で数学の勉強をしたことがなかったので「直角(perpendicular)」「分母(denominator)」「約分(simplify)」などの数学用語を重点的に復習していました。
一方で、課題は読解問題でした。趣味程度で洋書を読む程度だった私の読解スピードを、いかに現地アメリカの高校生が解くSAT®の問題構成に対応できるところまで引き上げられるか。そこに読解問題の攻略がかかっていたようなものだったので、とにかく練習あるのみでした。
時間を測って(ここ重要です)問題を解いて、分からなかった単語を洗い出して復習する。その繰り返しです。
* College Board(カレッジボード):米国大学入試の標準テストの一つであるSAT®や高等教育カリキュラムの策定・運営を行う非営利団体
Q. 試験勉強を高校生活と両立するために、スケジュールやモチベキープの工夫は?
まず試験日を決め、逆算して学習計画をデザイン。区切りを作りモチベもアップ!
私はもともと英語以外にも韓国語などの語学学習が趣味だったので、語学力テストなどはよく受けていました。どの言語学習においても、まずお金が許す範囲で「来年までに◯級を取る」と決めて先に試験を予約していました。
大体の語学力テストは3ヵ月〜半年先の試験を予約できるので、先に試験の日を決めて、残り数ヵ月の勉強スケジュールを自分でデザインする、といった感じです。そうすれば、ある程度逆算して勉強の目標を設定できますし、一旦勉強の区切りが見えるのでやる気も出ます。
Q. これから外部試験対策を始める人、今まさに頑張っている人にアドバイスを!
言語は自分を豊かにできるもの。英語圏の文化に触れるなど楽しむことを忘れずに!
大学受験や試験対策のために英語を勉強していると度々忘れてしまうのですが、本来言語というものは試験で高得点を取るためのものではなく、人と人を繋ぎ、自分をさらに豊かにできるものです(ということに私は韓国語を勉強しながら気づきました(笑))。
受験や試験が終わっても、グローバルな社会で生きる限り英語との付き合いは続くでしょう。なので、一番避けるべきなのは、英語を嫌いになってしまうことだと思います。単語帳やテキストと向き合うことに疲れてしまったら、息抜きに英語のドラマを見たり、小説を読んでみたり、音楽を聴いてみてもいいんです。英語圏の文化に触れてみることをお勧めします。
裏を返してみれば、SAT®を受けているようなアメリカの学生はそういった時間のほうが長いのですから、SAT®に必要な語彙を増やす鍵はそこにあるかもしれません。
とにかく自分を楽しませることが勉強のモチベーションを保つためには大切だと思います。そのように楽しみながら勉強して得た知識は、ただの試験対策に留まらず、その後の自分の人生にも活きる財産になってくれるだろう、というのが私の考えです。
いかがでしたか?
目標スコアの達成に向けて長文読解力・語彙力が課題だったというA.K.先輩。過去問演習・復習を学習の中心に据えた対策は、地道ながらやはり最も効果的といえそうです。足がかりとして専門の対策コースで始めたことは、学習スタイルに合っていただけでなく、同じく海外大を目指す仲間の頑張りを目の当たりにでき、学習のモチベアップにつながっていたかもしれませんね。
【海外進学・留学に関するお役立ち情報が満載!】
→Topページで海外進学・留学について知りたいキーワードを入力・検索できます
LINE公式アカウントはじめました!
無料の海外進学イベント情報や、最新の留学記事の更新を逃さず受け取れます!
→海外進学・留学ラボのLINEアカウントを友だち登録する
ベネッセでは、グローバルな進路を実現する多様な学習プログラムをご用意しています。丁寧な個別カウンセリングをもとに、あなたの希望に合わせた、「あなただけの海外留学・進学」をプロの知識と経験でしっかりサポートします。
ベネッセの海外進学プログラムでは
「海外進学にチャレンジしたい」中高生のためのイベントを随時開催中!
自分らしい進路実現に向けてぜひお気軽にご参加ください。
▼

- « 前の記事へ