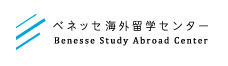留学生の先輩が本気でオススメ! 英語外部試験 高得点クリア術 ~ウェズリアン大学 Miho Y.先輩~
海外大学の出願に欠かせない「外部英語試験」の対策について、先輩たちの学習方法やスコアアップにつなげられた工夫などをお聞きしています。1回ずつの受験でSAT®、TOEFL®ともに目標スコアをクリアしたMiho Y.先輩は、どんな対策を行ったのでしょうか。
※ここでご紹介している内容は個人の体験です。実際に準備する際は、必ず最新の情報をご確認ください。

テスト特性を押さえた対策に加え、読書の幅・量を増やして準備。メモの取り方などマイルールも効果的!
今回の「ラボ協力隊」

Miho Y.先輩
アメリカ ウェズリアン大学 1年生。政治学・英語のダブル主専攻、東アジア学副専攻予定。
学びの選択肢や学生の多様性、大学院進学のしやすさ、将来携わりたい人権問題への研究が進んでいることなどから米国大学進学を決めた。
Q. 海外大出願のために受けた外部英語試験は?各テストを選んだ理由、時期も教えてください!
学力はSAT®、語学はTOEFL®を選択。まず模試を解いて相性を確認しました。
Miho Y.先輩が受けた外部英語試験
- 1. SAT®:高2の10月(1回のみ)
2. TOEFL®:高2の3月(1回のみ)
SAT®:高2の10月
学力試験はSAT®とACT®の中から選べたので、私はまず両方の模擬試験を解いてみました。それぞれの公式サイトはもちろん、対策ページや参考書も充実しているので、いろいろインターネットで検索してみることをおすすめします。
私は英語の読解には自信がありましたが、理数系が苦手だったので、ScienceセクションがあるACT®ではなく英文の分量が多いSAT®を選択しました。模擬試験を一度解くだけで時間配分の感覚や出題形式との相性がつかめるので、とりあえず挑戦してみてください!
TOEFL®:高2の3月
英語検定試験も学力試験と同様、まずは手ごたえを確かめたかったので、TOEFL®とIELTS™の模擬試験を解きました (Duolingo English Testは非対応の大学もあるため除外しました)。
大きな相性の違いは無かったのですが、複数回受験する可能性を考慮して、ラッキーなことに試験会場が最寄り駅にあるTOEFL®を選びました。
Q. 各テストの特徴は? 気をつけたいポイントもあればぜひ!
テストのクセ、会場で起こり得る状況を踏まえた訓練や事前シミュレーションを!
SAT®の特徴
私はペーパーテスト版の最終年に受験したので、現在のオンライン版と少し異なるかもしれませんが… 私が受験して感じた特徴を以下に挙げていきます。
Readingセクションは英文が長い上に時間が短いので、集中力が重要だと感じました。65分で合計5本のパッセージを読むのですが、内容は小説や科学的な記事など多岐に渡るため、前後の文章に引っ張られず頭を切り替えていくことが求められます。
対してWritingセクションは、実は受験者が何かを書くわけではなく、与えられた文章の文法や論理構造の正誤判定をしていくという「クセが強い」形式なのですが、こちらでは瞬発力が鍛えられました。文章の内容をあまり気にせず、パッパッと文法のミスを修正するスピード感が必要です。
TOEFL®の特徴
基本的にパソコンを用いての受験になるため、ペーパーテストに慣れている人はご注意ください!例えば、私は問題用紙にメモをとることで頭を整理する「書き殴り」タイプなので、画面を見るだけのパソコンでは集中力が削がれてしまいました。
また、会場によっては周囲の人とバラバラのタイミングでListening・Speakingセクションを開始することになります。私はこれを知らなかったため、Listening中に聞こえてきた隣の受験生のSpeaking音声に「え、私何か間違えた?」と不安になってしまいました。
TOEFL®の中でも最も高難易度と言われるListeningセクション(音源の再生時間が5~10分と長く、専門的な用語も多く登場するため)で気が散ってしまったことは、とても後悔しました。
何が起こっても動揺しないように、雑音がある環境で模試を解くなどしてシミュレーションを重ねると良いかと思います。
Q. 各テストの得点力アップにつながった勉強法は?
読書量を増やし「読む筋力」アップ!自分ルールを決めるのも効率よく解く鍵に。
SAT®の得点力アップ術
✓Reading …得意なほう
SAT®の対策は、公式の無料オンライン学習サービスであるKhan Academyを中心に行いました。ここでは長文読解におけるポイントがいくつかのUnitとして整理されており、講義動画を見る→練習問題を解く の繰り返しで効率よく勉強できる仕組みになっています。
ただ、受験の1か月前にようやく本格的な対策を始めた私にはしっかり動画を見る余裕など無かったため、論理的なインプットはそこそこに、様々な種類の英文に触れることを優先しました。例えば、私は英語の小説はよく読んでいましたが、学術的な文章には苦手意識があったため、毎日BBCなどニュースサイトのScience部門に目を通していました。
準備に余裕がある人や、そもそも英文に慣れていない人はセオリーを押さえることも大事ですが…。SAT®のReadingはスタミナ勝負なので、とにかく読書量を増やし「読む筋肉」を鍛えることがおすすめです!
✓Writing …得意なほう
WritingはReadingと比べて文法などの正確な知識が求められるため、よりセオリーベースの対策を行いました。Khan Academyは自分の進捗を記録し苦手分野を分析してくれる機能があるので、例えば「私はsubject-verb agreementが弱点なんだな」と、復習内容を絞ることができます。
ただ、どれほど知識をつけても応用ができないともったいないため、こちらも「読む筋肉」を鍛えることが重要です。読書量を増やすことで、仮に文法のロジックを知らずとも「なんとなく」でわかる問題が増えていき、スピーディーに解くことができます。
私は小説やニュース記事、過去問題などを手あたり次第読んでいました。そもそも読書が好きだったので、英文も段々と楽しめるようになり、嬉しかったです!
TOEFL®の得点力アップ術
✓Listening …苦手なほう
TOEFL®のListeningは英語圏での大学生活を模した「講義」や「会話」の読解が中心となります。私は「講義」の対策を重点的に行いました。
このパートでは教授がある分野について解説し学生と交流するのですが、生物学から経済学まで、聞いたことがないような専門用語が主題となることがほとんどです。私は知らない単語が登場すると頭が真っ白になる癖があったので、本番形式の練習を重ね、細かい単語よりも物事の因果関係に集中できるように努力しました。
また、メモは情報を整理する上で重要な手がかりとなるため、効率的なメモ方法(例えば、私は△⇔!などの記号を多用しました)を自分なりに確立すると便利かもしれません。
✓Reading …得意なほう
TOEFL®はReadingもアカデミックな内容がほとんどです。1本の文章に20分ほどしか割けないので、SAT®のReadingと同様、普段から沢山の英文に触れることで頭を「英語脳」に切り替えていきました。
私は前述の通り、スクリーン上の文章を読むとどうにも気が散ってしまうので「1パラグラフを読み終えたら1回内容を整理する」といった自分なりのルールを定めていました。
✓Speaking …苦手なほう
Speakingは、海外経験が少なく一条校に通っていた私が最も苦労した部分でした。自分の主張を述べる問題や、数十秒の講義を聞きそれを口頭で分析する問題があるのですが、どれも準備時間は15〜30秒ほどしか与えられません。
必ずしも最適解でなくとも、何かしらの答えを素早く組み立てるスピード感が試されます。私はこの「組み立て」の練習を特に意識しました。
模擬試験を繰り返し「まず結論を述べること」「Therefore, however, additionallyなどの転換語がスッと出てくるようにすること」「自分が話すかもしれない内容を踏まえたメモをとること」などのポイントを頭に叩き込みました。
この練習はネイティブスピーカーに評価してもらえれば一番なのですが、私は回答を録音し自分で確認していました。2〜3回録音を聞く→改善点を洗い出す→回答をやり直す というプロセスを繰り返すことで、英語が口に馴染むようになり、達成感を得ることができました!
✓Writing …得意なほう
WritingもSpeakingと同じように、自分の意見を述べる設問と、読んで聞いた内容を要約する設問があります。私は後者の要約に苦手意識があり、論拠を省いてなんとなくの感覚で文章を書いてしまう癖があったので、模擬試験においてはブレインストーム(良し悪しを問わずアイデアを多数出してから整理する手法)を練習しました。
10〜20分という限られた時間の一部をブレインストーミングに割くことには抵抗があるかもしれませんが、たったの1分「主題はこれで、根拠はこれで、この順番で書こう」と確認するだけで、実際の執筆作業がグンと楽になります。
また、書きながら細かいワードチョイスにこだわると振り返りの時間を削ってしまうので、ひとまず最後まで書ききり、後から修正・肉付けするということを強く意識しました。
Q. これから外部試験対策を始める人、今まさに頑張っている人にアドバイスを!
最初から完璧を狙わず「やってみる」!実際に解くうちにポイントが見えてきます。
「とりあえずやってみる」ことを大切にしてほしいです!私は大雑把・ゴリ押しタイプだったので、とりあえず模擬試験を解きまくり、ありとあらゆる勉強法を試しました。
高得点を獲得するに越したことはありませんが、問題に触れることで見えてくる相性や自分の弱点があるので、パーフェクトにこだわらず勉強してみてください。
心から応援しています!!
いかがでしたか?
まず模試を解いてみて受験するテストを決めたMiho Y.先輩。短期間で目標スコア到達まで仕上げられたのは、問題内容・構成などの特性と自分の弱点、クセと照らし合わせて、理解を深めたうえで必要な対策に絞り込んで効率よく進められたからこそ。「とりあえずやってみる」をぜひ実践していきましょう!
【留学生の先輩が本気でオススメ! 英語外部試験 高得点クリア術:シリーズ記事をチェック!】
アメリカ / グリネル大学 Kanata M.先輩[TOEFL® / SAT® / IELTS™]
アメリカ / ウェズリアン大学 Miho Y.先輩[TOEFL® / SAT®](この記事)
【海外進学・留学に関するお役立ち情報が満載!】
→Topページで海外進学・留学について知りたいキーワードを入力・検索できます
LINE公式アカウントはじめました!
無料の海外進学イベント情報や、最新の留学記事の更新を逃さず受け取れます!
→海外進学・留学ラボのLINEアカウントを友だち登録する
ベネッセでは、グローバルな進路を実現する多様な学習プログラムをご用意しています。丁寧な個別カウンセリングをもとに、あなたの希望に合わせた、「あなただけの海外留学・進学」をプロの知識と経験でしっかりサポートします。
ベネッセの海外進学プログラムでは
「海外進学にチャレンジしたい」中高生のためのイベントを随時開催中!
自分らしい進路実現に向けてぜひお気軽にご参加ください。
▼