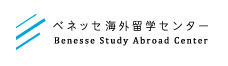海外大での学び・課外活動体験談④~私が大学で得た一生モノの経験やスキル~
今回はシリーズの最終回。前回までの記事でもご紹介したように先輩たちの大学はそれぞれ個性に溢れていて、どの大学も魅力的なポイントがあります。そして、大学での華やかな経験がある一方で、「いやなことや、苦労を乗り越える」という貴重な経験も得られます。今回は、それらを“一生もののスキルや経験“として、ご紹介!最後には、これから海外進学をする高校生に向けたメッセージも語ってくださっています。

シリーズ<海外大での学び・課外活動研究>
1週目:① 私の大学ならでは!の特徴&個性
2週目:② 私の大学の“面白い学びスタイル&!ウワサ!な授業”
4週目:④ 私が大学で得た一生モノの経験やスキル◀︎ 今ココ!
今月の「ラボ協力隊」

Lisa. I. 先輩
オーストラリア シドニー大学 (The University of Sydney)経済学部経済学専攻の卒業生。
TAFE NSW Ultimoキャンパスで Diploma of International Businessにも通学経験在り。
高校時代の短期留学経験から日本で勉強するだけでは知ることができない事があると知り、さらに色々な事を体験するため海外に進学。 卒業後日本に帰国し、現在はコンサル会社に勤務中。

Megu K. 先輩
アメリカ ニューヨーク大学(New York University) 4年生。
得意だった英語を生かし、リベラルアーツ教育を通して自分のやりたいことを探索するため海外進学を選択。
専攻は、メディア・文化・コミュニケーション(

H. K. 先輩
カナダ トロント大学(University of Toronto)卒業生。 小さい頃からの宇宙飛行士になりたいという夢を追って海外進学を決意。 大学では、数学と統計学の二分野を専攻。現在、日本に帰国し外資系企業に就職。

Lilia T. 先輩
アメリカ カリフォルニア州立大学(California State University)4年生。 将来やりたい職業を叶えるにはアメリカの大学で学ぶのが一番良いと考えて海外進学を選択。 現在の専攻は、テレビ・映像メディア研究(Television, Film, and Media Studies)。
Q. 先輩にも大学で苦労したことは?どうやって乗り越えましたか?


Lisa. I. 先輩
自信があったはずの英語に悩まされましたが、改善策を自分で見出し成績を好転換しました!
私は、大学で英語の面で苦労をしました。私は高校時代、英語が得意科目だったため、自信を持って海外進学したのですが、大学入学当初は周りのレベルについていくことができず、授業やチュートリアルのディスカッションで全く発言できなかったり、地道に勉強を続けていたにも関わらず、試験で思うように結果が出せなかったりする苦労がありました。
しかし、その悔しい思いをしないための改善策を考え、実行するプロセスを繰り返したり、自分ひとりで勉強するだけでなく周囲の友人や教授の力を借りてわからない事を恥ずかしがらずに聞いたりするうちに、内容を「暗記する」勉強方法から「自分の言葉で理解する」方法に変わっていき、授業内容がハイレベルになっても良い成績が取れるようになりました。

Megu K. 先輩
ルームメイトと気が合わなかったことも。おかげで英語力が伸びました!
私は最初、ルームメイトに恵まれなかったことが嫌でした。大学1・2年のルームメイトとはあまり仲良くなかったのですが、特に1年生の時はクレジットカードを盗んだ疑いをかけられたり、同じ部屋で勉強しているのにルームメイトが大音量で彼氏と映画を見たり…と大変な思いをしました。
嫌でしたが、学校での仲間にはとても恵まれていたので、勉強を外で行ったり、ルームメイトと過ごす時間を減らしたりして気分転換をしてすっきりしていました。また、進学後最初からこのような苦労する場面に出くわしたことで自己防衛、自己主張をする英語力がものすごく身についたとも言えます…!


Lilia T. 先輩
校舎が急な丘の上でとっても大変!前向きに乗り越えたい、と思ってます(笑)。
私はテレビジョン・映画・メディア学科なのですが、その学科で利用する校舎が丘の上にあるんです…それも、とても急な丘!学校の周りの道路をじゅんぐり渡りながら、急な坂をずっと登って行かないといけないので、正直遠いし、時間もかかります。まだ私がその校舎で授業を受けることはないので通う頻度は少ないのですが、今までに“学科主催のイベント”や“新入生・編入生のオリエンテーション”で何度か訪れましたが、とても大変で…これからが思いやられます。でも、前向きに捉えると…良い運動のコースです!(笑)

H. K. 先輩
日本食のありがたさを痛感する食生活。食べ盛りの頃にはきつかったです。
勉強での苦労はもちろんですが、それよりも苦痛だったのは、生活面での苦労、特に食事です。何しろ学食がとにかく驚くほど高額で恐ろしくまずかった!ことが嫌でした。
日本だと学食といえば、学生が好きなメニューや健康的なものがそろっていてお金にも優しい!というイメージですが、まったく違いました。大学に入学すると食堂で食べ放題の“ミールプラン”というのを必須で購入します。ミールプランとは、一年分の学食費を専用のカードに入れて一年間そのカードで学食を買うという、学食の前払いみたいな制度です。私の寮ではサラダ、スープ、フライドポテト、ハンバーガーが固定で置いてあり、あとは日替わりでメニューが変わっていました。(日替わりといっても4週間ごとに同じメニューが回ってきていたような気がします…。日曜日の朝はパンケーキとワッフルのローテーションのみでした。)
基本的に好きなものを好きなだけとってその分払いますが、さすがに3か月目にはわくわく感も消え、たまの爆弾メニューにハラハラしていました。今でも記憶に残っている爆弾メニューはきのこのキッシュ?パイ?で、味のしないどろどろが激甘のパイ生地に包まれているものでした。あれはアウトでした!
Q. 先輩の大学は、学生の経験やスキルを支えるためにどんなサポートがありますか?


Lisa. I. 先輩
個別に教えてくれるチューターのサポートがあるので授業内容の理解を深めることができます。
まず、学生全体の学習面のサポートとして、博士課程の学生(チューター)が15名程の学生に対して教えるチュートリアルがあります。レクチャーだと講義中心で、教授に直接質問する機会が限られていますが、チュートリアルは授業内容のディスカッションや実践形式で問題を解くことが中心のため、他の学生と協力しながら理解を深めることができます。そして、それに加えて毎週1時間、各チューターが設定している時間にオフィスを訪れると、個別で質問することができるというものもあります。
生活面のサポートとして、大学構内のいたるところに寮があり、国内外の学生に関わらず入寮することができます。多くの寮は食事がついていますし、新しく入寮した学にはサポーターがついてくれるので、初めてオーストラリアに来た学生でも安心して学校生活を送ることができる環境が整っています。
シドニー大学では、留学生へのサポートも充実しています。留学生専用の相談窓口があり、授業の取り方や卒業後の就職活動の相談、日々の生活の相談等ができます。また、学生が運営する留学生コミュニティに所属すると、セメスター中に開催されるイベントのお知らせを受取ることができるため、自分の学部・学科・学年以外の友人とのネットワーク作りの場となっていました。


Lilia T. 先輩
学習面ではチューターが、寮はRAが、進路相談はカウンセラーが…と各方面にサポーターがいます。
学生全体へのサポートは、しっかりしていて様々な分野で相談役がいます。例えば、授業内容や科目で分からないことがあると、同じ科目をとっている学生やその分野を専攻している上級生が指導をしてくれるチューター制はもちろんありますし、寮であればリーダー役となるRA(Resident Assistant)がいて面倒を見てもらえますし、学校にも私生活の悩みから進路の悩みまで相談できる様々なカウンセラーがいます。
特に私は学校の寮に住んでいたので、RAの人に助けてもらうことが多かったです。RAは、一人につき5部屋程(人数にすると15人くらいだったと思います)を担当していて、寮生活で分からないことがあったらRAの人にいつでも連絡できるようになっています。たまに各部屋を訪問して様子を聞きに来てくれますし、連絡事項があればそれを伝えに来てくれるような存在です。
そして、私は学校の進路カウンセラーの方々にもお世話になりました。今の大学への編入前のコミカレ時代は、確実に編入できるように一緒にプランを立ててもらったり、合格後の手続きの流れなどを質問して相談していました。編入後も卒業に向けていつ、どの授業をとるのかカウンセラーの方と一緒にプランを立てました。
ちなみに、物資的なサポートもありますよ。テスト期間になると生徒会のような機能があるオフィスにブルーブック(テストで使う、罫線だけが描かれた薄いノート)やマークシートが置かれ、生徒が無料でもらえるようになっています!ブルーブックやマークシートはキャンパス内のブックストアでも売っているのですが、無料でもらえるということを知っている人は多くないようで、知っている人はお得にゲットできます!でも、テスト期間終盤になるとなくなってしまうので、テスト期間になったら早めにもらいに行っています。
留学生へのサポートでいうと、International Office(留学生担当のオフィス)がどの学校にもあると思うのですが、私もそういったところで国外の渡航の際のアドバイスやI-20(アメリカで外国人対象の学生がアメリカにいる資格があるということを証明する入学許可書)についてのサポートを受けました。I-20を持っている留学生なら日本とアメリカを行き来する際は必ず学校のオフィスのサインが必要なので、International Officeを利用することは多いと思います。私の場合は、コミカレ時代も今の大学でも利用していましたが、International Officeの対応は丁寧で早くI-20のサインも当日か次の日には終わることが多くて助かっていました。


Megu K. 先輩
留学生が多い大学ならではのしっかりとしたサポート体制。留学生同志の情報交換も盛んです。
ニューヨーク大学は、サポートという面では大学独自の特別なシステムはありませんが、必要最低限のサポートシステムの質は高いと思います。例えば、ライティングでサポートが必要な場合はライティングセンター、インターン探しや就活でサポートが必要な場合はキャリアセンター、寮内で問題に直面したらResidential Assistant (RA)などその道のプロフェッショナルからサポートを受けられます。
ニューヨーク大学は留学生が多いので、サポート体制はきちんと整っていると思います。が、一番役に立ち、相談しやすいリソースは“同じような立場の他の留学生”だと思います。留学生が多いこともあって留学生同志の情報がとても盛んに飛び交います。ビザや授業の口コミなど、自分のリサーチでは知りきれない情報がたくさん出回っているので、他の留学生と一緒にサポートしあえる環境はとても頼りにしています。

H. K. 先輩
学生皆に学習面、精神面のサポート、そして、留学生にも何でも相談できる留学センターがあります。
学校全体の学生のサポートには、“メンタルクリニック”が利用できたり、勉強の仕方で相談したいことがあれば“勉強専門の相談室”がありました。私は1年生の頃よくその相談室に行って、効率の良い勉強の仕方や大学内にあるリソースを教えてもらったり、小論の技術を上げるためのワークショップを紹介してもらいました。
留学生のサポートにも、“留学センター”というものがあって、私は利用したことがありませんが、留学生全般の悩み等はそこで聞いてもらえるみたいです。留学生が集って行われるイベントなどもよく催されていました。
Q. 先輩が大学で得た“一生モノのお宝スキル”はありますか?


Lisa. I. 先輩
“自ら解決する”、その行動力と精神が身に付いたことが何よりの宝です。
私が海外の大学に進学して得た一番のスキルは、“チャレンジ精神”だと思います。私は日本にいた頃からシャイで、人前や新しく知り合った方と話す事が苦手でした。しかし、オーストラリアでは、言語が異なる環境で、困っている時に助けてくれる両親がおらず、自分が何を解決したいのか・どのような助けを求めているかを周囲に伝える必要がありました。
そのプロセスを何度か繰り返すうちに、自分が行動しないと何も解決できないと思うようになり、生活費を稼ぐためのアルバイト先や就職活動を見据えたインターンシップ先を探して応募したり、大学のネットワークイベントで新たな人と出会って自分のコミュニティの輪を広げたりしました。
その結果、自分が心地良い環境にいるだけでは経験できなかった事が経験できました。社会人になった今でも様々な事に挑戦していますが、自分自身の仕事の幅を広げられたことで、新たな機会を与えていただけた等、大学で得たスキルが活きているなと感じています。

Lilia T. 先輩
すごい数と量のエッセイを同時進行で期限までに書き上げるスキルが身に付きました。
私は、大学に通い始めてエッセイを書くのが早くなり、書くためのアイディアをどんどん出せるようになりました。それは、ものすごい量のエッセイを同時進行で書く鍛錬を積んだからです。例えば、今学期は3〜5ページのエッセイを6枚程、10ページのリサーチペーパーを1枚、毎週1〜2ページの感想文を1枚書き、他にも小さいエッセイなどがありました。それらは、それぞれ違う授業なので一週間に何ページもエッセイを書くペースです。もちろん全て期限があるのでそれを守って書き続けていると、“期限までに余裕をもって終わらせるというスキル“が磨かれました。
元々転入前のコミカレの時もたくさんの課題を早めに終わらせることが得意ではありましたが、渡米してそのような課題をこなしていくうちに、たくさんエッセイを書くことに慣れました。

H. K. 先輩
専攻の数学を通して得たスキルは、“何時間でも集中して考え続けられること“です。
“考え続けること”でしょうか。私の専攻は、純粋数学だったのでテストはすべて証明することでした。3時間で一問を解くという世界だったので、毎日2問ぐらいをやっていた私には6時間ほど考えつづけるのなんて苦ではありません。でも、逆に数学専攻の弊害は記憶力が劇的に落ちたことです。なるべく脳のスペースを考えることに使いたかったので、最小限のことしか覚えなくなりました。それぐらい考え続けることにエネルギーと時間を費やしていたので、自信があるスキルになりました。


Megu K. 先輩
話すスピードが速いニューヨーカーに対応できる英語力が身につきました。
一生の宝、それは“英語の会話力”です。ニューヨーカーは、アメリカの中でもとても早口でお喋りな人と言われているのですが、本当にみんな早口でお喋りなので、ニューヨーク大学に行ったからこそハイスピードな会話についていけるスキルが身につきました。最初は授業もついていけず、周りが話していることに圧倒するだけで終わっていましたが、今ではディスカッションをリードすることができるようになりました。
Q. 最後に、海外進学を目指す高校生へ「入試対策」アドバイスと応援メッセージをください!


Lisa. I. 先輩
自分で考えて柔軟に対応することが大切。勉強した内容だけが身の回りに起こるわけではありません!
私は高校時代、授業で習ったことや本の内容を暗記する勉強をしていましたが、実際に海外で生活してみると、覚えていたはずの事が伝えられない事や、知っている表現では適切に対応できない事がたくさんあり、毎回もどかしい気持ちを感じていました。その理由は、自分の頭で考えたり、実際に自分が使う場面を想像したりしなかったからだと思います。海外の大学では、授業で学んだ内容を踏まえて、自分がどう考えたか、そこから何を学んだかが重要になります。したがって、海外の大学を目指す方は、普段の生活の中でも自分の頭で考える事を意識していくと良いと思います。

H. K. 先輩
高校生の間はとにかく興味のあることについての時間を楽しんでほしいです。
高校生の間はとにかくその時間を楽しんでほしいです。自分の少しでも興味のあることには手を出す。「あんなことできる高校生かっこいいな」と思うことを自分がやる。体育祭で団長をやったり、トルストイを読んでみたり、テストで学年1位をとったり、文化祭でバンド組んでみたり。いろんな経験を通して発見した自分の新しい側面は必ずどこかで活きてきます。みなさんの高校生活が大切な思い出でいっぱいになりますように。

Lilia T. 先輩
現地で英語力に自信をつける!治安の良し悪しを把握する!が、大事です。
私の大学は留学生が比較的少ないので、私のように編入せず入学するとしたら、アメリカに住むことに早く慣れて自分の英語力にも自信をつけることが大切だと思います。コミカレでも現在の大学でもそうですが、自分が学びたいことや将来目指しているものがないと周りの友達はどんどん先に進むので、出来るだけ目標を明確にするとスムーズな学生生活が送れると思います。
あとは行きたい大学の周辺地域をよく調べて、治安の良い場所と悪い場所を把握しておくことが大事です。みなさんが海外進学を決めた際は、楽しい生活が送れることを祈っています!

Megu K. 先輩
ぜひ進学前に“自分の個性とは何か?“を自分に問いかけてみてください。
ニューヨーク大学は、個性的な学生を集めたら何らかの化学反応が起こると信じている大学だと私は考えています。ニューヨーク大学への進学を考えている場合、“なぜNYUで自分が興味のある学問を勉強したいのか”と考える以外に“What kind of person am I ?(自分ってどんな人なのだろう)”と自分にしかないユニークなアイデンティティについて今のうちから考えてみるといいかもしれません。
いかがでしたか?
“一生モノの宝になる経験やスキル”は、海外に進学した先輩たちだからこそ大学独自の学び、環境での体験を通して得られたものでしたね。4回のシリーズで先輩たちの個々の大学を様々な切り口で紹介をしてきましたが、先輩たちの国や大学が自分の目指すものではないとしても、大学の特徴の捉え方、学びの楽しみ方、設備・施設の情報…などから進学後の姿を想像しやすかったのではないでしょうか。目指す大学についても同じような情報を調べてみると期待が高まりそうですね。
※この記事でご紹介している内容は2021年2月23日現在の情報に基づいています。