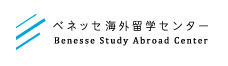海外大での学び・課外活動体験談②~“面白い学びスタイル&!ウワサ! な授業”~
海外大での学びとはいったいどのようなものでしょうか。独特な単位の取得、特徴のある専門学科があるなど学びの仕組みが大学で違ったり、多岐に渡る専門分野ごとの授業、有名教授の授業など、それぞれの大学ごとに名物授業やバラエティ豊かな授業が存在しているはずです。そこで今回は、先輩たちの大学の学びの仕組み、授業について語っていただきます。

シリーズ<海外大での学び・課外活動研究>
1週目:① 私の大学ならでは!の特徴&個性
2週目:② 私の大学の“面白い学びスタイル&!ウワサ!な授業”◀︎ 今ココ!
3週目:③ 私の大学の“感動!ビックリ!なイベント”
4週目:④ 私が大学で得た一生モノの経験やスキル
今月の「ラボ協力隊」

Lisa. I. 先輩
オーストラリア シドニー大学 (The University of Sydney)経済学部経済学専攻の卒業生。
TAFE NSW Ultimoキャンパスで Diploma of International Businessにも通学経験在り。
高校時代の短期留学経験から日本で勉強するだけでは知ることができない事があると知り、さらに色々な事を体験するため海外に進学。 卒業後日本に帰国し、現在はコンサル会社に勤務中。

Megu K. 先輩
アメリカ ニューヨーク大学(New York University) 4年生。
得意だった英語を生かし、リベラルアーツ教育を通して自分のやりたいことを探索するため海外進学を選択。
専攻は、メディア・文化・コミュニケーション(

H. K. 先輩
カナダ トロント大学(University of Toronto)卒業生。 小さい頃からの宇宙飛行士になりたいという夢を追って海外進学を決意。 大学では、数学と統計学の二分野を専攻。現在、日本に帰国し外資系企業に就職。

Lilia T. 先輩
アメリカ カリフォルニア州立大学(California State University)4年生。 将来やりたい職業を叶えるにはアメリカの大学で学ぶのが一番良いと考えて海外進学を選択。 現在の専攻は、テレビ・映像メディア研究(Television, Film, and Media Studies)。
Q. 先輩の大学に「学びのスタイル」の特徴はありますか?また、単位取得や授業の組み方のコツがあれば教えてください!



Megu K. 先輩
専攻の選択肢が豊富!自分の興味に合わせて入学後に専攻の変更もスムーズです。
よく「リベラルアーツと総合大学の違い」で、リベラルアーツは自分が専攻したい学問を探すことができて、総合大学はより専門性が高いから専攻が決まっている人に向いていると言われることが多いと思いますが、実際はそんなことはあまりなくて、逆に総合大学の方が専攻の選択肢が豊富にあり、専攻を変えやすいようになっていると私は思います。
入学した時から同じ専攻を忠実に勉強している人は本当に一握りです。多くの学生は大学に入学して色んな授業を取って自分の興味が違うところにあると気づいたり、自分が専攻しようとしていた学問が面白くないという理由で違う専攻を選んだりと専攻を変える人がほとんどです。
というのも専攻の変更は非常に簡単で、専攻の必修単位だけ2年の終わりまでに取っていればすぐに変更が出来ます。特例は世界的に有名な芸大(Tisch School of Arts)とビジネススクール(Stern School of Business)だけで、その2つへの変更は再度受験をしないといけないシステムはありますが、だからと言って専攻が出来ないという訳でもないので自由に自分が学びたい専攻が選べます。
学び方のコツとしては、アメリカの大学にはEasy A授業と言われる授業があります。これは、教授が採点に甘い(Aが取りやすい)授業を指します。最初はEasy Aの授業に惹かれますが、私は逆にこういう授業の方が点数を取りづらい上、あまり何かを学んでいる実感がないことに気づきました。採点は厳しいかもしれないけど熱心に授業をしてくれる教授の授業を取ることでたくさんの刺激があると思うので、授業を選ぶ際は少しチャレンジしてみるのもいいと思います。


H. K. 先輩
朝方?夜方?など自分の生活スタイルに合わせて授業を組み立てられたので、効率よく学べました。
トロント大学での学び方をおおざっぱに言うと卒業までに20単位とらなければならず、一つの専攻を終えるのにだいたい9単位とらなければなりません。また卒業までに、文化・芸術、宗教・思想、社会、生物・環境、理数科学の5分野から最低1授業ずつとらないと卒業できません。
1年生の時は割と自由にどの分野の授業もとることができ、2年生にあがって専攻が決まると、その専攻を終えるために履修しなければいけない授業のリストが渡されます。そのリストにあるものを卒業までにとりつつ、残りの単位数を興味のある授業で埋めるという感じです。
単位や授業の取り方ですが、自分の生活スタイルに合わせて履修できると良いと思います。私は朝型タイプで夜に自主的に勉強するのが苦手だったので、授業はほとんど夜にとって(20時から22時とか)、朝4時に起きて自習をしていました。
授業だと夜は嫌でも集中しないといけなかったので、この組み方が自分には一番合っていました。あとは知り合いに“取りたい授業”、“取らないといけない授業”の評判を聞いて、なるべく難しいのが一学期に集まらないように計画をたてると楽に勉強ができます。


Lilia T. 先輩
コミカレから大学への編入がしやすい!編入することを見据えてコミカレ時代も授業を企てることが大事です。
私の大学は、編入生の数が多いので、学びの仕組みとしては編入しやすいところでしょうか。留学生にとって学費は安いとは言えませんが、現地の学生(特にカリフォルニア在住のアメリカ人学生)にとってはコミュニティーカレッジ(コミカレ)の学費はとても安いので、出来るだけコミカレで必要な一般教養などを終わらせてから4年制大学へ編入する人が多いのです。環境的にも私の大学の周りにはコミカレが多く存在しているのも理由かもしれません。クラスメイトにもいろんなコミカレから編入して来ている人がいました。
授業の選び方のコツは、入学してすぐに卒業までの履修プランを作ることです。学校には、編入専門のカウンセラーや学部のカウンセラーがいると思うので、そのような人たちに相談する時間を設けて「自分が卒業・編入までにいつ、どのクラスを取りたいのか」を全部組み立てると良いです。その後の学期ごとに行う履修登録がとてもスムーズに行えます。
編入を考えている場合は、編入先の大学で入りたい学部・専攻を頭に入れながら“その前にコミカレでどの授業をとらなければいけないのか”をよく調べることをお勧めします。また、希望制で夏学期や冬学期の授業をとることもできるので、夏休みや冬休みを利用して1〜3クラスほど履修しておくと、計画通りに卒業に向けての授業を受けやすいので良い案だと思います。

Lisa. I. 先輩
1科目ごとの課題&試験の量・質がヘビー!試験までに計画的に勉強することがおすすめです。
オーストラリアの大学は2学期(セメスター)制。欧州や北米の大学と異なり、1セメスターあたりの科目が4つと少ないのが特徴です。ただし、1科目が毎週3時間のレクチャーと1時間のチュートリアルで構成されているため、4科目だけでも平日は一日中授業がある日がほとんどです。それに加え、1セメスター中に各教科で中間試験、期末試験と課題2~3つが出されるため、毎週授業の内容をしっかり予習・復習しておき、試験前に余裕を持って勉強に取り組むことができるよう、計画的に勉強する必要があります。
シドニー大学は学部や専攻が多様なため、授業の選択肢が多いことが特徴ですが、学部や学科毎に1年から3年までの必修科目が設定されています。必修科目の単位取得条件が満たされていれば選択科目は比較的柔軟に選択できるため、必修科目の課題や試験の負担を考慮し、年間でバランスよく選択することが重要になります。
TAFE(州立の職業訓練専門学校)は、コースごとに授業カリキュラムが決められているため、自分で授業を組むことはありませんが、各コースに含まれている内容を理解して選択することが重要だと思います。
大学ではより高度な内容を限られた時間の中で理解していく必要が
Q. 先輩の大学でしか経験できない面白い、ウワサな授業を教えてください!



Megu K. 先輩
教授がマシュマロを学生に投げることから始まる!?ウワサな授業。この授業を受けた学生は幸せになります!
<ウワサの名物授業>
専攻に関わらず“ニューヨーク大学の大学生なら、誰もが一度は取ってみたい!”と思う授業があります。それは、”Science of Happiness”という授業です。
この授業はChild & Adolescent Mental Health Studiesという副専攻に含まれている一つの授業なのですが、「人々を幸せにする方法が学べる授業で「この授業を取った人は本当に少しだけ幸せになれる」という噂があります。
最初の授業では、必ず教授が学生に向けてマシュマロを投げるらしく、「何かを投げるという動作は暴力的にも関わらず、それがマシュマロだったらなぜみんなは嬉しくなっちゃうんだろう…」という問いから始まるらしいです。去年は、ある一人の生徒が投げられたマシュマロを遠い席から投げ返して教授の頭に当てたことで、授業全体が湧いた…と聞くぐらい大学でも毎年ウワサな授業です。
<面白いと感じた授業>
私の専攻であるメディア・文化・コミュニケーション学の必修科目の授業で“Media & Cultural Analysis”という授業があります。これは、他の授業で学んだセオリー(理論)を使って実際にデジタルメディアを作り出す授業なので、グループワークやフィールドワークが中心でした。
その授業の課題の一つに”Ethnography Project”という、普段は文化人類学や社会学で使用される調査方法を使って、「身近な空間がどのように人々の行動に影響を与えているのか」について研究し、動画を作り上げる課題がありました。その授業で知り合った、今でも仲良くしている4人と「大学の図書館を題材にする!」と決め、私たちは一週間に渡って図書館で勉強をしている人たちを観察し、実施したインタビューから分かった驚愕エピソードを動画内で再現しました。
調査によると、期末前は集団自習室で友達とカラオケをしたり、一週間図書室に寝泊まりしてトイレで体を洗ったり、コーヒーメーカーを持ち込んでその場でコーヒーを作ったりする人がいる…とのことだったので、友達と静かな図書館でドラマチックにそれを演じ、動画に撮りました…笑。個人的に授業とは思えないほど楽しい授業でした。


H. K. 先輩
あのビートルズ!に関係のある教授が教える熱い授業は、大学の目玉授業です。
<ウワサの名物授業>
私の大学で名物授業だったのは、「ビートルズ」の授業。これは名物というより大学の“目玉授業!”じゃないかなと思います。授業開始前は、“まぁ「ビートルズの授業」ってタイトルなら、ビートルズの曲を聞いて、感想でも書くのかな…“くらいに思っていたんですが、実は、教授はあのポールマッカートニーと一緒レコーディングしたことのある人で、それはもうすごい熱量!の授業でした。軽い気持ちで取り始めた授業ですが、熱すぎる授業になってしまい最後には一番悩まされた授業になりました…笑。でも、ビートルズについて少し詳しくなれたので、すべて良し…!です。
<面白いと感じた授業>
面白い!と思ったのは、「日本のおばけ」という授業です。柳田国男の遠野物語に始まり、日本の歴史をなぞりながら日本人の中で発展していく「妖怪」という概念、途中で現れる「怪獣」。日本人にとってのそれらの意義を文化的背景とともに学ぶ、という授業でした。
毎授業前に出される課題には読み物もありましたが、ほぼ毎回「
ちなみに私は最終論文で「千と千尋の神隠しに垣間見える日本経済バブル期の闇」について書きました。作品に深入りし過ぎた結果、以前のように純粋な気持ちで「千と千尋の神隠し」が観られなくなったのが残念です…!


Lilia T. 先輩
「バットマン」のワンシーンに音付け編集をする授業は、自分の想像力が駆け巡る面白さでした。
<面白いと感じた授業>
面白かった授業は、私がコミュニティーカレッジに通っていた時に受けた授業なのですが、毎週フィールドワークに行っていた授業です!この授業はカリフォルニアの生態や気象について学ぶ授業だったのですが、授業の初日以外は州立公園などに行きハイキングのような感じで自然の中を歩き回りました。
スケッチをしながら歩いたり、途中でお昼ご飯を食べながら行われる授業で、なんだか遠足みたいでした。大変だったことは、広い公園の中をひたすら歩くので体力的にキツかった…です。しかし、毎週違う場所を訪れることができたので、授業を受けながらカリフォルニアの自然を満喫できてとても貴重な体験でした!一回干潟にも行ったりもしました。海と山どちらも訪れることができる授業でとても楽しかったです。
そして、大学の授業で面白かったのは、映画の“サウンドデザイン”の授業です。“サウンドデザイン”とは効果音や、コンピューターで作った音を映画のシーンや動きに合わせるものです。私がその授業を受けたときは15人くらいが受講したのですが、コロナの影響のためオンラインで行われました。各自のパソコンにソフトウェアをダウンロードして、教授に渡された音源を、編集したりしてコマーシャルや動画に合わせました。
学期末の課題は、「バットマン」の映画のワンシーンが無音の状態で教授から渡され、銃声音、爆発音、殴る音、救急車の音、環境音(風なども!)を編集してそのシーンを完成させるものでした!音の素材を自らネットで見つけたり、パソコンで作ったりして作業をするという個人で取り組む課題だったので、自分の想像力と学んだことを活かせる点がよかったです!
<ウワサの名物授業>
大学でウワサな授業は、私の友達が取っていた授業なのですが、日本の文化や映画、アニメを見てそれを分析する授業があるみたいです。日本好きの学生が集まる授業のようで、グループでのプレゼンテーションも行ったみたいです。私は受講していないのですが、その話を聞いた時に「日本人として、現地の学生と日本の文化について一緒に話し合ったり、日本のことを教えられたりする授業は楽しそうだなぁ」と思いました!

Lisa. I. 先輩
仲間と課題に取り組む楽しさを知った統計学の授業。面白くて好きな教科になりました。
<面白いと感じた授業>
私は専攻の経済学に加えて統計学の授業が好きだったため、選択科目で受講していました。授業の内容としてはちょっと難しい話なのですが、膨大なデータを基に、世の中で起きている事象の要因と結果をモデル化(表す)するという内容で、ソフトウェアを使って行う授業でした。
私は、元々コーディングという作業(コンピューター言語でプログラムのコードを書くこと)の知識や経験が無かったのですが、その授業でグループ課題を行った際に、メンバーが色々な作業の仕方(コードやモデル毎の活用方法)を教えてくれました。
互いにアイディアを出しながら最終の形の精度を高めることができたので、結果的にグループ課題で良い評価を得ることができました。その経験から、“自分ひとりで勉強する時には得られない楽しさ”に気づくきっかけとなったため、統計学が好きな教科になったのだと思います。
<ウワサの名物授業>
大学で有名な授業ですが、東アジア経済の発展に関する教科の特別授業です。それは、シドニー大学を卒業して、アジアでスタートアップを始めたという起業家を招いて行われた授業なのですが、ビジネス系の学生の中で人気になっていました。
私が受講した年は、“工場で排出された二酸化炭素を吸収して、別素材に作り変える技術“を推進するスタートアップ企業の起業家が来校してくれました。事業を始めたきっかけや企業してからの苦労、今後のビジネス展開に向けて現在取り組んでいる事などを直接聞くことができ、非常に良い経験だったと思います。
TAFEで国際貿易の交渉、手続きなど実践型授業を体験。知識だけじゃなく現実感ある授業が面白い!
TAFEで扱う教材は、本屋で一般の方も購入できる教科書ではな
私は、職業訓練校のTAFEではInternational Businessを専攻していましたが、特に“国際貿易の科目の授業”が印象に残っています。その科目では、授業の一環として、学生20名程がそれぞれ担当の国を決めて、各国間の貿易協定の取り決め交渉や輸出入品目ごとに必要な手続き等を模擬的に行う内容がありました。この授業を通して、知識として学んだ内容を単純に覚えるだけでなく、実際に自分自身の経験として活用する事で、より深く内容を理解する事が出来る事も学べたのが良い経験になったと考えています。
いかがでしたか?
先輩4人のお話から、どの大学も学生の可能性を最大限に伸ばすため、「ならではの学びシステム」や、そこでしか経験できないマニアックな授業まで用意されていることがわかります。またそこでの学びを通して、先輩たちは自身の興味関心に気づいたり、友人との関係性を深めるなど学びの豊かさを感じていました。もし数年後、海外大進学をかなえられたら、どんなお気に入りの授業を見つけられるかな?をいうことを考えるのもワクワクしますよね!
次回は、先輩たちの大学で行われている驚き!感動!のイベントについてお聞きしていきます。
※この記事でご紹介している内容は2021年2月9日現在の情報に基づいています。