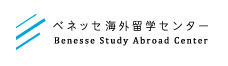【連載】松藤百香のルワンダ渡航記⑥

東京大学1年生の松藤百香(まつふじももか)です。
春休みを利用して教育系ボランティア活動のため、ルワンダに来ています。
ルワンダでの生活やボランティアの様子、そこで感じたことを日記形式で発信しています。
大学進学後の過ごし方や、アフリカに興味がある方の参考になれば嬉しいです!
そして、今回ついにルワンダ渡航記は最終回!
松藤百香のルワンダ渡航記①はこちら
28日目 – 田舎の公立小学校へ
本日断水3日目。もはや珍しいことでもないので特記せず。
今日は3.5時間かけて田舎町gashoraの公立小学校見学へ。
バスに揺られること3.5時間。バスの爆音ノリノリ音楽、乗客の大多数が大声で電話している光景にもすっかり慣れた。
到着してまず驚いたのは田舎の静けさ。舗装された道は一本だけで、それ以外は赤土が広がっている。歩いていると、四角くて小さな家々が並んでいて、その周りで遊ぶ子どもたちの姿が目に入った。ここでは学校に通っていない子どもが多い。子どもが学校に行かない理由として親が学校の必要性を感じていないことも一因らしい。教育が生活の一部になっていないため、「学校に行くのが当たり前」という概念がそもそもないのかもしれない。そういった人たちにも教育の必要性をわかってもらいたい。
ふと、同居人のルワンダ人大学生が言っていたことを思い出した。
「先進国の人たちは、アフリカを水も電気もない森だと思ってるでしょ? 違うよ、水道も電気もちゃんと通ってるよ!」
彼女たちは都会育ちだからそう言っていたのだろう。でも、ここには水道も電気もない家がある。この現実を、彼女たちが知らないことに驚いた。そして、私も日本の現実をどこまで知っているのか、ふと、考えてしまった。

29日目 – 田舎の学校のほうが英語ができる?
今日は、担当している 小4と同じ学年の授業を見学。
この学校は、保育園から高校までを持つマンモス公立校で、設備も広さもしっかりしている。

驚いたのは、生徒の英語能力の高さ。「田舎のほうが教育の質は低いだろう」という勝手な先入観があったが、ここではむしろ、私が教える学校の生徒より英語を話せていた。
英語が話せる = 英語の教科書を理解できる = ハイレベルな授業ができるということ。想像以上に発展的な内容で驚いた。
もうひとつの違いは、生徒たちが落ち着いていること。私が教える学校では、生徒が頻繁に席を移動し、騒がしくなることが多い。理由を考えてみた。
- 1.クラスの人数 → ここでは50人、私が教える学校は70人。
- 2.教室の構造 → 私が教える学校の教室には真ん中に柱があって黒板が見えない子がいる。だから席を移動してしまい収拾がつかなくなる。
- 3.体罰がない → ここでは体罰禁止が徹底されている。

真ん中の柱を挟むようにして席が配置されている
政府は学校での体罰を禁止しているものの暴力で躾ける文化が根強く、学校でも先生が生徒を叩くのが普通になっている。実際、一部の親は「学校で体罰を取り入れるべきだ」と訴えることもあるらしい。でも、この学校では暴力を使わずとも生徒が静かに授業を受けている。外国の団体が支援をしており、体罰をしない方針が徹底されているという。
「罰を与えて抑え込むのではなく、尊重することで自主的な行動を促す」その可能性を感じた1日だった。

帰りのバスでは、景色を眺めながらぼーっとしていたら、気づけば到着。帰宅すると、水はまだ戻っていなかった。水がないときは隣の家から水道水をもらったり、雨水をためて水を確保している。
30日目 – 提案書を作る
今日は、新しい校長先生に会った。とても教育熱心な方で、「日本の教育メソッドを先生たちに教えてほしい」と言われた。これはチャンスかもしれない。
これまで1ヶ月間、生徒や先生の様子を見て、何ができて何が難しいのかが分かってきた。
その経験をもとに、具体的な改善提案書を作ることにした。
これまで「日本の目線で何かを提案しても、余計なお世話なのでは?」と思っていた。
でも、gashoraの学校を見学し、外からの視点で学校を変えることができる可能性を感じた。他の国からの目線による改革が学校を変え、先生や生徒の意識も変えていく。そして、その学校に通う未来の多くの生徒たちの将来をも変えていく。単なる一時的な関わりだけではなく、継続的な影響を残したい。
帰宅すると水が復活していた! でも今度は 電気がつかない。最近毎晩停電だから、もはや特に驚かない。


停電中の町の様子
31日目
今日は 毎朝8時20分からの全校集会(アセンブリー) に参加するため、早めに家を出た。すれ違う人の顔ぶれも新鮮で楽しい。途中立ち寄ったお店の店員さんに 「ルワンダ大学の学生?」 と聞かれて、思わずニヤリ。最近、じっと見られる回数が減ってきた。すれ違う人が私を見慣れたからかもしれないし、何より私自身がこの街に馴染んできたからかもしれない。
今では、綺麗な景色を見てもカメラを構えなくなったし、ソファーやドアを自転車で運ぶ光景にも驚かない。道を歩く猿やヤギたちも、もはや日常の一部になった。
そんな私の変化が、周りの反応を変えているのかもしれない。
提案書の反応
完成した学校の改善提案書をまずは仲の良い先生に見せることにした。
主な提案内容は以下の4つ。
① 机の配置を見直す → 黒板が見やすい座席配置にすることで、授業の集中力を上げる
② 宿題チェック制度の導入 → 回答を丸写しする生徒が多いため、提出と確認の仕組みを作る
③ クラス管理のための生徒リスト作成 → 先生が生徒の状況を把握しやすくするため
④ 毎日の計算&英単語テストの導入 → 学力向上のための習慣化

手書きの提案書を提出
先生は「生徒にとって良いと思うことは何でもやる。なんでもっと早く提案してくれなかったの?」と言ってくれた。受け入れてもらえたことが本当に嬉しかった。
特に机の配置変更は、すぐに試すことに。前の黒板に向けて机を整列させ、後ろの黒板を使うときは反転させる方式を提案。先生も 「すごくいいアイデア!」 と気に入ってくれた。
生徒たちも大喜びで、突然ミュージカルのように歌い出す(笑)。
先生のフィードバックをもとに少し修正して明日校長先生に提出する。提案書を出すのが楽しみになってきた。

聴覚支援学校での出会い
午後は聴覚支援学校(小学校)を見学。この学校は、中学・高校の生徒も受け入れており、聴覚障害のある子どもと障害のない子どもが一緒に生活する寮制の公立学校になっている。
そこで、流暢な英語を話す女の子と仲良くなった。そしてなんと、私が教えている学校の卒業生だったことが発覚!
「小学校の頃はどうだった?」と聞くと、「最初は英語も話せなかったけど、だんだん慣れていくものだよ。」と、穏やかに微笑んでいた。
これまで、「生徒たちは十分な理解ができないまま英語で授業を受けて意味があるのか?」と疑問に思っていたけど、彼女を見ていると、それは杞憂だったのかもしれない。
ただ、彼女が小学生の頃は1クラス40人ほどだったそう。今は70人超え。この人数の増加が、教育の質の低下につながっているのでは? そんな疑問が頭をよぎった。

32日目
今日は提案書を校長先生に直接渡すつもりだったが、会議で忙しそうだったため、提出は月曜日に持ち越すことにした。
ポスター作りの授業と70人の大移動
今日の授業は ポスター作り。校外に出てポスターを見に行くことになり、生徒は大興奮。70人で大移動。これ、日本だったらありえないよな…。自由すぎるこの感じ、やっぱり好きだ(笑)。

現地の買い物 – 驚きの値下げ幅
ランチの前にショッピングへ。現地の友人から「1人で行くとぼったくられるから気をつけて。」と言われていたので、同居人(ルワンダ人)が一緒に来てくれた。
スウェットを買おうとすると、最初 「2,000円」 と言われたが、友人の交渉で 最終的に600円に。
…え?とんでもない値下げ幅に思わず笑ってしまった。
ケニア人の友人を見送りに首都キガリへ
午後からは帰国するケニア人の友人を見送るため、再びキガリへ。先週も3人で来たばかりだけど、これが最後かと思うと寂しいな。
たった2週間の関係だったのに、ここまで仲良くなれたことに驚いている。私が中学2年生でフィリピンに留学したときは、みんなの会話についていくのに必死で、一年かけても深い関係を築くのは難しかった。
でも今は、育った環境も価値観も何もかも違う彼女と、英語を通じてここまで分かり合えた。お互いにとって第一言語ではない英語なのに、心を通じ合わせることができた。そのことが、なんとも言えず嬉しい。

キガリに着いて、軽くKFCに立ち寄ったが、値段が高すぎてびっくり。ルワンダにはマクドナルドやスターバックス、バーガーキングなど他の大手ファストフードチェーンはない。そのため、値段もかなり高めに設定されているらしい。
そして宿(友人の家)に到着。疲れも溜まっていたのか、友人の肩を借りて爆睡してしまった。
33日目 – 別れと、初のエチオピア料理
昼前までみんなで爆睡。昼食を食べたあと、またみんなで昼寝し夕方ごろに空港へ友人を見送りに。
感動的な別れになるかと思いきや、まさかのチェックインが終了間近でバタバタ。写真を急いで撮って、慌ただしくあっさりとお別れ。またいつか会える気がする。

その後、人生初のエチオピア料理を食べに行った。「美味しい!」と思ったのも束の間、
酸味のある生地がどんどんキツくなっていく。見た目以上にお腹に溜まる料理だった。独特の味に圧倒されながら、異文化の食体験を堪能した。

食後は、先週と同じくKigali Convention Centerへ。夜景をバックに写真を撮り帰宅。たくさん寝たはずなのに、ベッドに入るとあっという間に眠りに落ちた。
34日目 – 大雨と助け舟
日曜日はショッピングへ。でも、ほとんどのお店が閉まっていた。ルワンダの大半はキリスト教徒なので、日曜の朝はみんな教会に行く。そのためお店もやっていないらしい。
薄暗いショッピングモールをぶらぶらして昼ごはんを食べた。することもないのでそろそろ帰ろうとバイクで移動しようとしたら突然の大雨。全身びしょ濡れになりながら、なんとかバス停へ。

でも、バス停からチケット売り場までは少し距離がある。深さ5センチほどの水たまりに行く手を阻まれ、どうしても渡れず足が止まった。
立ち尽くしていると、おじさんが現地語で何かを言いながら、背中を差し出してきた。
迷う間もなく、気づいたら私は彼の背中にいた。
水しぶきをあげながら水たまりを渡ると、周りで雨宿りしていた人たちが大歓声をあげていた。まるで何か偉大なことを成し遂げた気分でなんだか楽しかった(笑)。
バスに乗り込んだ頃には、疲労もピーク。3.5時間の長旅を乗り越え愛しの我が家へ、やっぱり家のベッドが一番落ち着く。
明日から学校。頑張ろう。
最後に – 読んでくださった皆さんへ
ここまで読んでくださり、本当にありがとうございました。想像を超える出会いと発見に溢れた毎日は、驚きと学びの連続でした。この日記を通して、ルワンダの教育や文化の多様さ、そして挑戦することの楽しさが少しでも伝わっていたら嬉しいです。
これからも、自分とは異なる世界を、好奇心と敬意を持って体験していきたいと思います。
松藤百香
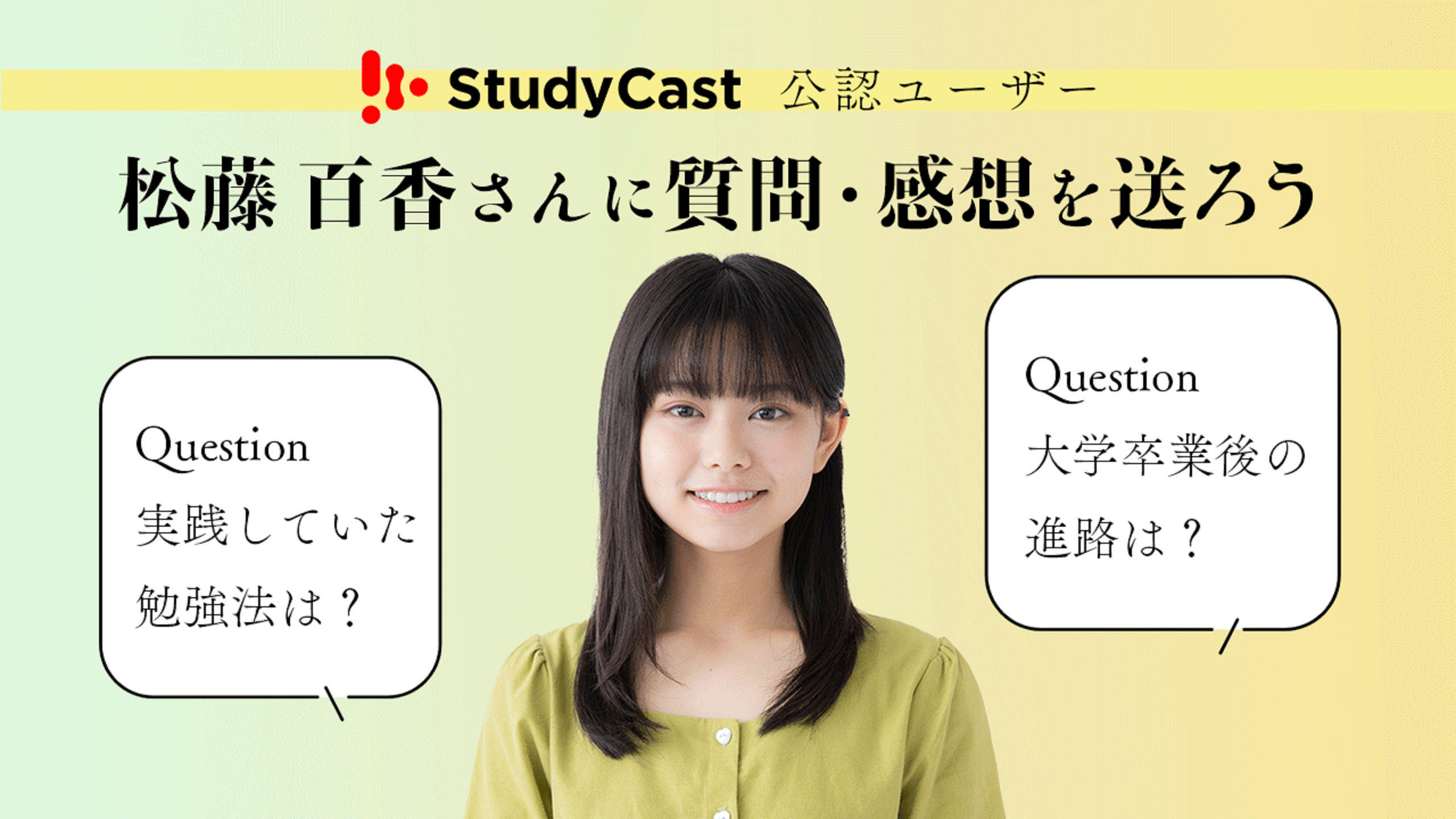
4/1(火)更新記事にて、松藤さん本人が寄せられた質問にお答えします!
過去の渡航記はこちら
- « 前の記事へ